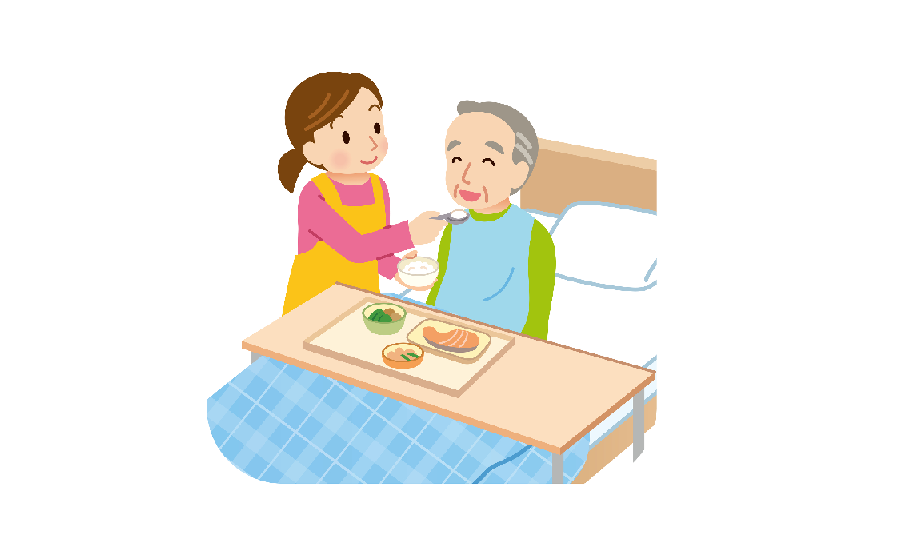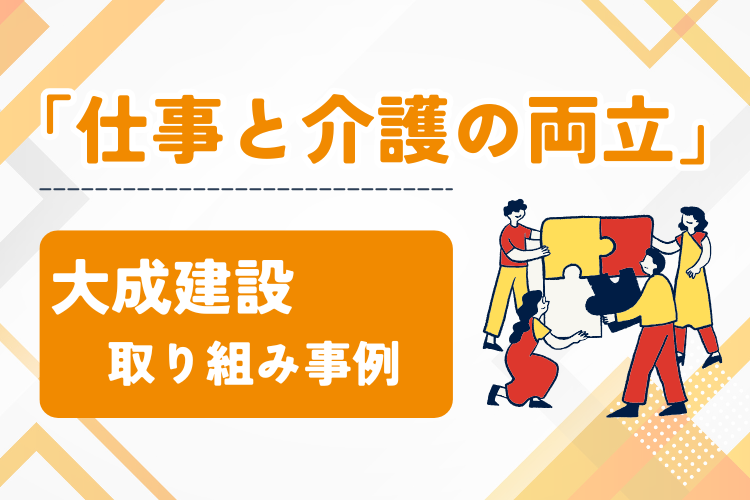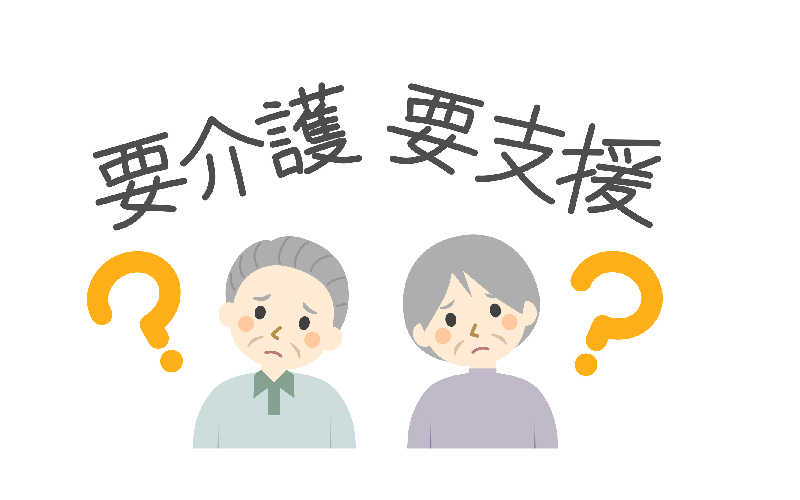身近な人が要介護5の状態になり、「要介護5はどのような状態?」「自宅で介護をすることは可能なのか?」と不安を抱いている人もいるのではないでしょうか。要介護5とは、7段階ある要介護認定の中で最も症状が重い区分。食事や入浴、排泄など日常生活全般において介護を必要とする状態です。今回は、要介護5に認定される基準や受けられる介護給付サービス、利用できる施設について紹介します。ご家族の介護で悩まれている方はぜひ参考にしてください。
要支援・要介護の基本的な情報は以下の記事で紹介しています。
要支援と要介護の違いは?認定基準や使えるサービスの違いを解説
目次
・要介護度5とは
・要介護5で受けられる介護給付サービスとは
・障害者控除を受けられる?
・利用できる施設と費用の目安
・まとめ