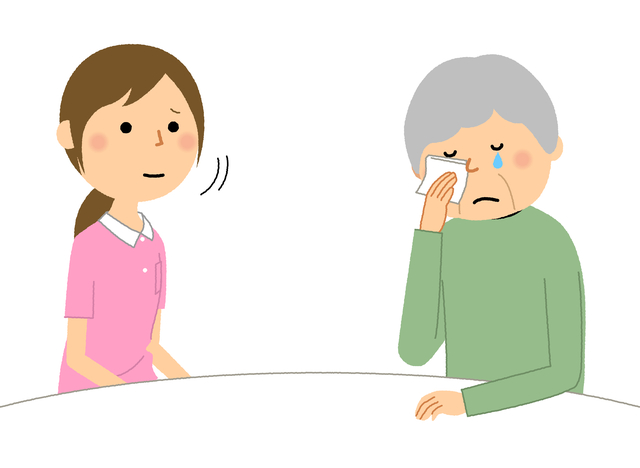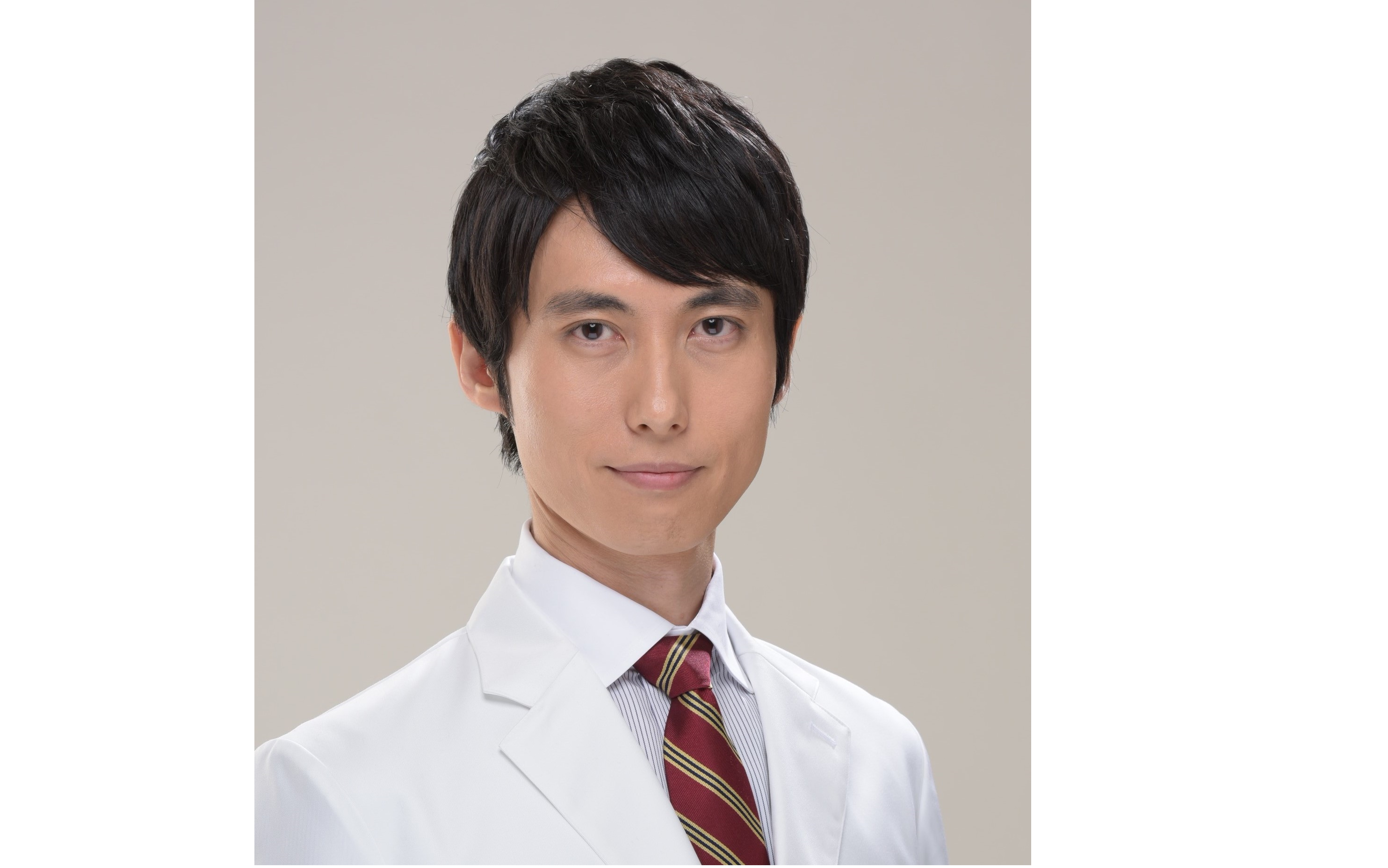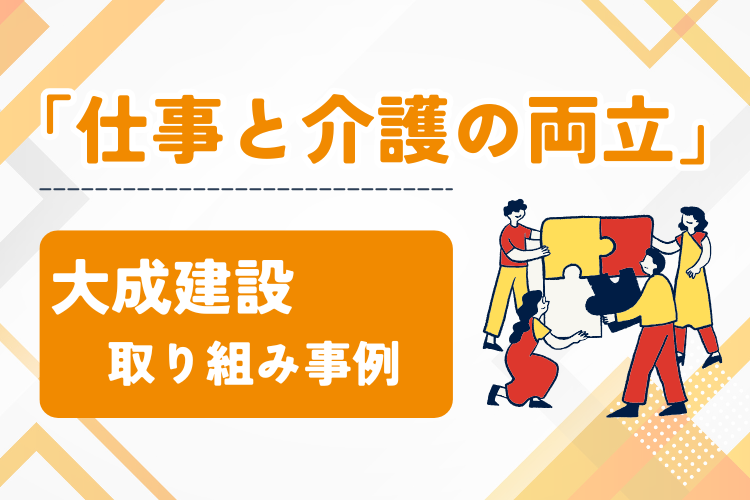高齢者介護は、介護をする側である介護者にも身体的な負担や精神的なストレスがかかる可能性があります。中でも認知症の介護は先が見えにくく、症状の進行とともに対応が難しくなりますので、長期間に渡る場合は、介護者に相当な疲労やストレスが蓄積されていくこともあります。その結果、介護者自身の健康が損なわれてしまうことも珍しくありません。
本記事では、介護負担を軽減し、ストレスをなるべくため込まないようにする方法を解説します。記事を参考にストレスの原因を理解して、自分に合った解消方法を見つけてください。
目次
・介護の疲労や悩みがストレスの原因に
・介護ストレスが引き起こす「介護うつ」とは
・介護ストレスを軽減するポイント
・
介護サービスを積極的に活用しよう
・まとめ