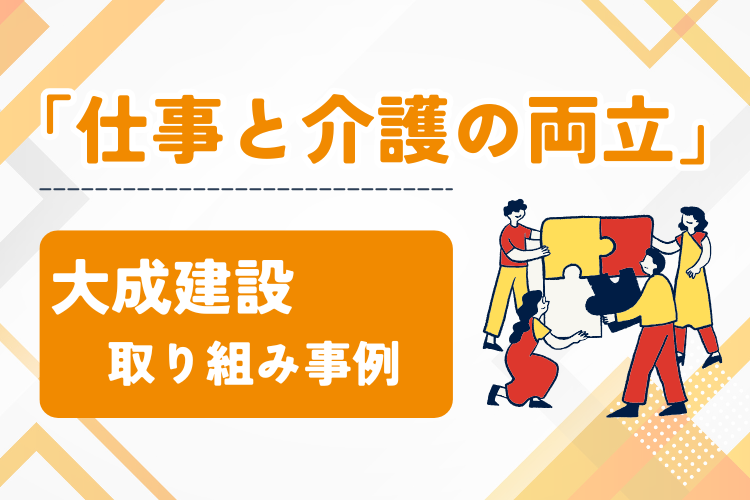認知症の診断は、ご本人にもご家族にも大きな衝撃をもたらします。支援する側・される側という関係のなかで、両者にとってより良い付き合い方をしていくためにはどうすればよいか、悩む方も多くいらっしゃいます。
今回は認知症当事者の丹野智文さんと、公益財団法人「認知症の人と家族の会」代表理事の鎌田松代さんをお招きし、異なる立場から認知症と向き合う二人に、これからの時代に必要な支援のあり方や目指すべき共生社会の姿をお話いただきました。
丹野 智文 氏
宮城県仙台市在住。2013年、38歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断される。診断後仙台市内の自動車販売会社で就労を継続。同時に、認知症当事者として認知症関連の啓蒙活動や、認知症当事者が元気になるための企画、仕組みづくりに取り組む。2023年には自身の半生を描いた映画「オレンジ・ランプ」が公開された。
【関連記事】若年性認知症と診断されたあの日から10年 〜認知症当事者 丹野智文さんの歩み〜
【関連記事】~若年性認知症当事者 丹野智文さんインタビュー~ 「自分で決めて、自分で動く」ことが当事者や家族の笑顔に
鎌田 松代 氏
公益社団法人認知症の人と家族の会代表理事。看護師として滋賀医科大医学部付属病院や特別養護老人ホームなどで勤務し、義父の介護を期に介護離職し、その後父母の認知症介護も行う。1990年に家族の会に入会。2019年に事務局長就任を経て、2023年6月に代表理事就任。
【関連記事】「認知症の人と家族会」新代表インタビュー(前編) 鎌田松代さんと認知症の歩み
【関連記事】「認知症の人と家族会」新代表インタビュー(後編) 認知症を「自分事」に 手を差し伸べ合う社会を作っていく
目次
・認知症になっても、工夫次第で変わらない生活ができる
・失敗から生まれた工夫が自信につながる
・今を一生懸命生きることが認知症の備えになる
・「認知症になっても安心できる社会」、「安心して認知症になれる社会」を作る