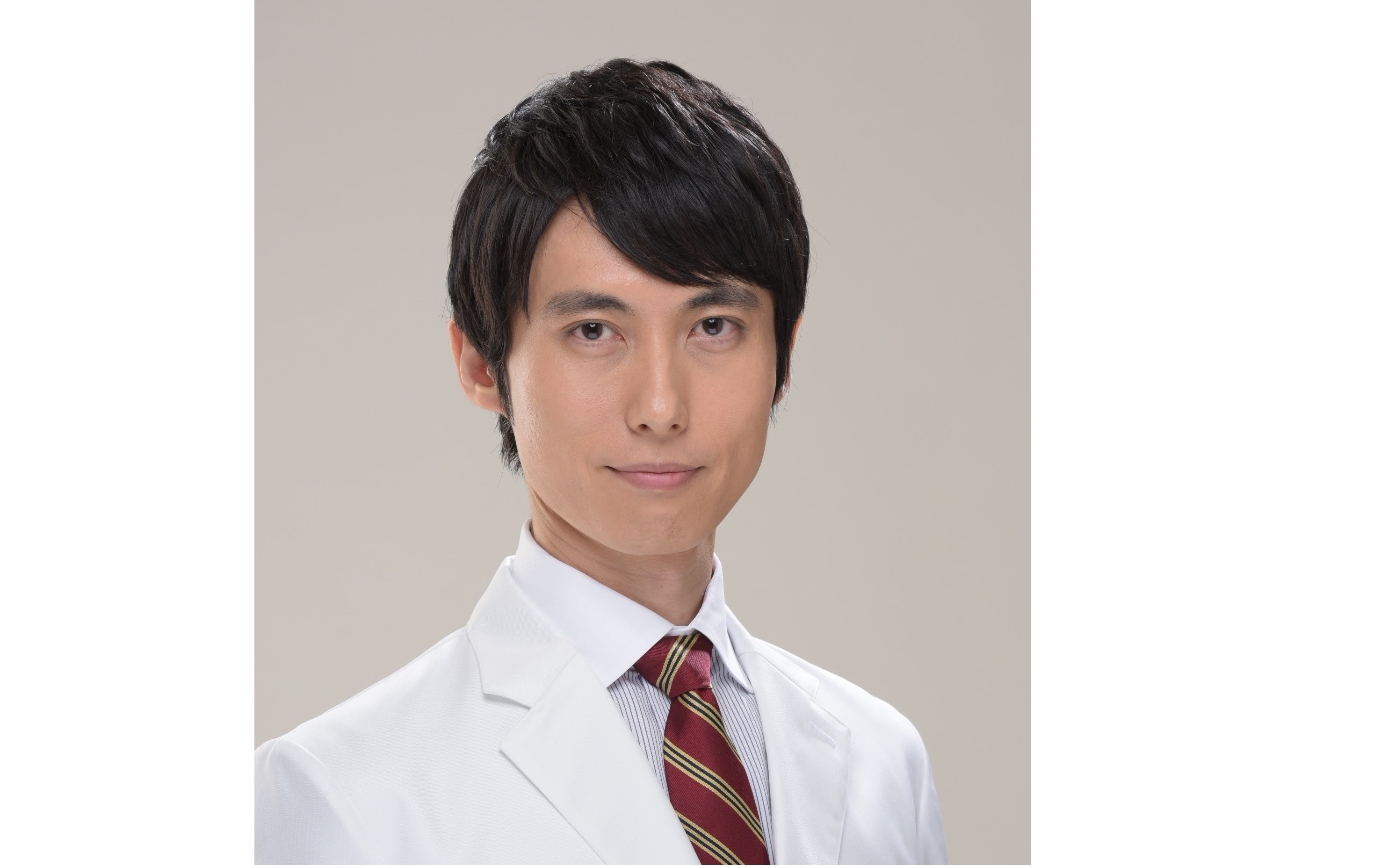認知症の治療方法とは
「認知症になったら治らない」そんな言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。しかし、完治だけが治療ではありません。ここでは、認知症の治療に対する基本的な考え方を解説します。
認知症の治療は進行抑制と機能改善
アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症、前頭側頭葉型認知症などに代表される多くの認知症を完治させる治療法は、まだ確立されていません。しかし、進行を抑制することはできます。そのため、認知症の治療は、「進行を遅らせる」ことと「日常生活の支障となっている機能を改善する」ことを目的に行われます。
具体的には、薬を服用し脳機能の低下要因となっている疾患にアプローチする薬物療法と、薬を服用することなくリハビリテーションなどにより脳の機能を活性化させる非薬物療法が行われます。加えて、身近にいる家族や介護者の対応や接し方が、認知症の治療に大きな影響を与えます。
残された機能を維持し、日常生活の支障となる症状を軽減・改善することで、たとえ認知症でも穏やかに普通の暮らしができることを目指し、治療の効果が上がれば介護者の負担軽減にもつながります。
治すことができる認知症
上記で解説した認知症以外に、治療が可能な認知症もあります。それが、脳腫瘍・慢性硬膜下血腫・正常圧水頭症・脳血管障害などが要因となっている認知症です。脳外科手術など外科的治療によって、これらの疾患を治療することで、認知症の症状を改善できる可能性があります。