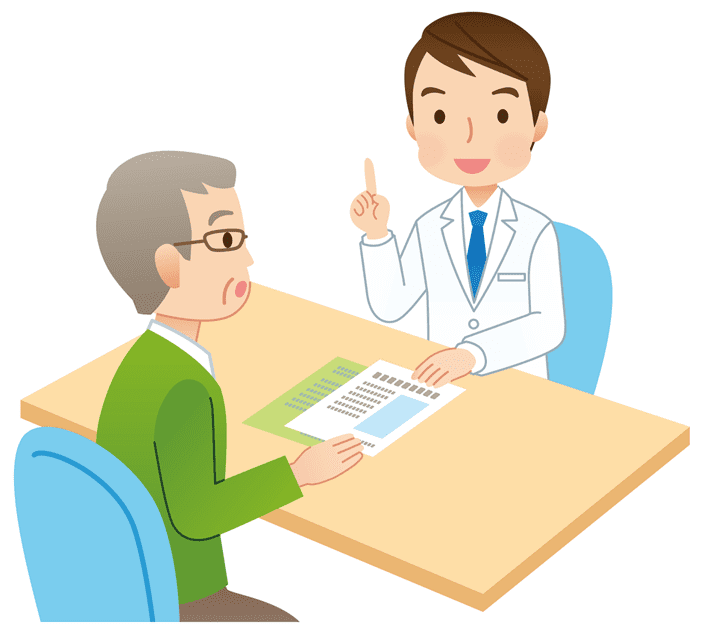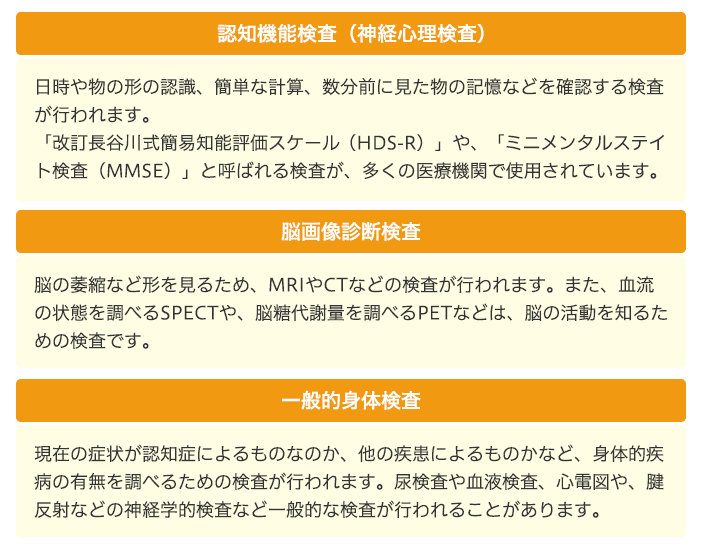認知症の疑いがある場合の相談先について
自身や家族に認知症の疑いがある場合、どこに相談をすべきか、悩む方も多いでしょう。生活環境や症状などによって、専門医に相談することが難しいケースもあります。状況に応じた、複数の相談先を紹介します。
地域包括支援センターに相談する
かかりつけ医がいない場合や、本人が病院を嫌がる場合もあるでしょう。そのようなときはお住いの地域を管轄する地域包括支援センターに相談しましょう。
地域包括支援センターとは、高齢者の生活に関わる総合相談窓口です。地域の高齢者が健康で安心して暮らせるよう、生活や介護に関する幅広い相談を受け、必要なサービスに繋ぎます。初めから地域包括支援センターに相談すれば、認知症と診断された際も、その後の要介護認定やケアマネージャーの選定など、相談がしやすくなるという利点もあります。
地域包括支援センターについての詳細は、こちらの記事(地域包括支援センターの役割とは?活用方法や相談事例をわかりやすく解説)で解説しています。
かかりつけ医に相談する
認知症に対する不安があるときには、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。
体調が悪くなったときや健康診断の時に、気軽にかかれる近所の病院や診療所はありますか? かかりつけ医は身近で頼りになる地域の医師です。必要なときには専門医療機関の紹介もしてくれます。病気のたびに違う病院にかかっていると、その都度同じような検査が必要になり、本人への負担も大きくなります。体調を崩したときに毎回相談できるかかりつけ医がいれば、ちょっとした変化にいち早く気づいてもらえることもあるでしょう。ぜひ日頃から何でも相談できる近所のかかりつけ医を見つけておきましょう。
かかりつけ医が認知症の専門医でなくとも心配はいりません。かかりつけ医の中には認知症サポート医による認知症研修を受けている医師もいます。認知症サポート医とは、地域のかかりつけ医に認知症の診断などに対するアドバイスを行ったり、認知症の研修を行う医師のことです。かかりつけ医のもとで認知症の診断ができない場合も、適切な医療機関につないでくれます。
専門の医療機関を受診する
認知症の診療を専門的に行う「物忘れ外来」や専門のクリニックが増えてきました。また、医療と介護支援を繋げる専門機関、認知症疾患医療センターも各都道府県や都市で設置が進められています。大学病院や総合病院では、「精神科」「神経科」「神経内科」「老年病内科」「老年内科」などで認知症の診察や治療を行っているところがあります。しかし、いきなり大きな病院を訪ねるよりも、かかりつけ医からの紹介状があるとスムーズです。
病院を選ぶ際には、「かかりつけ医と連携が取れる」「通いやすい」といった点も重要なポイントとなります。往復に時間がかかったり、待ち時間が長いような場合、本人だけでなく介護者の負担も増えるからです。普段の通院はかかりつけ医、検査時や容体の急変時などの入院には専門医、というように、使い分けができる環境が望ましいでしょう。