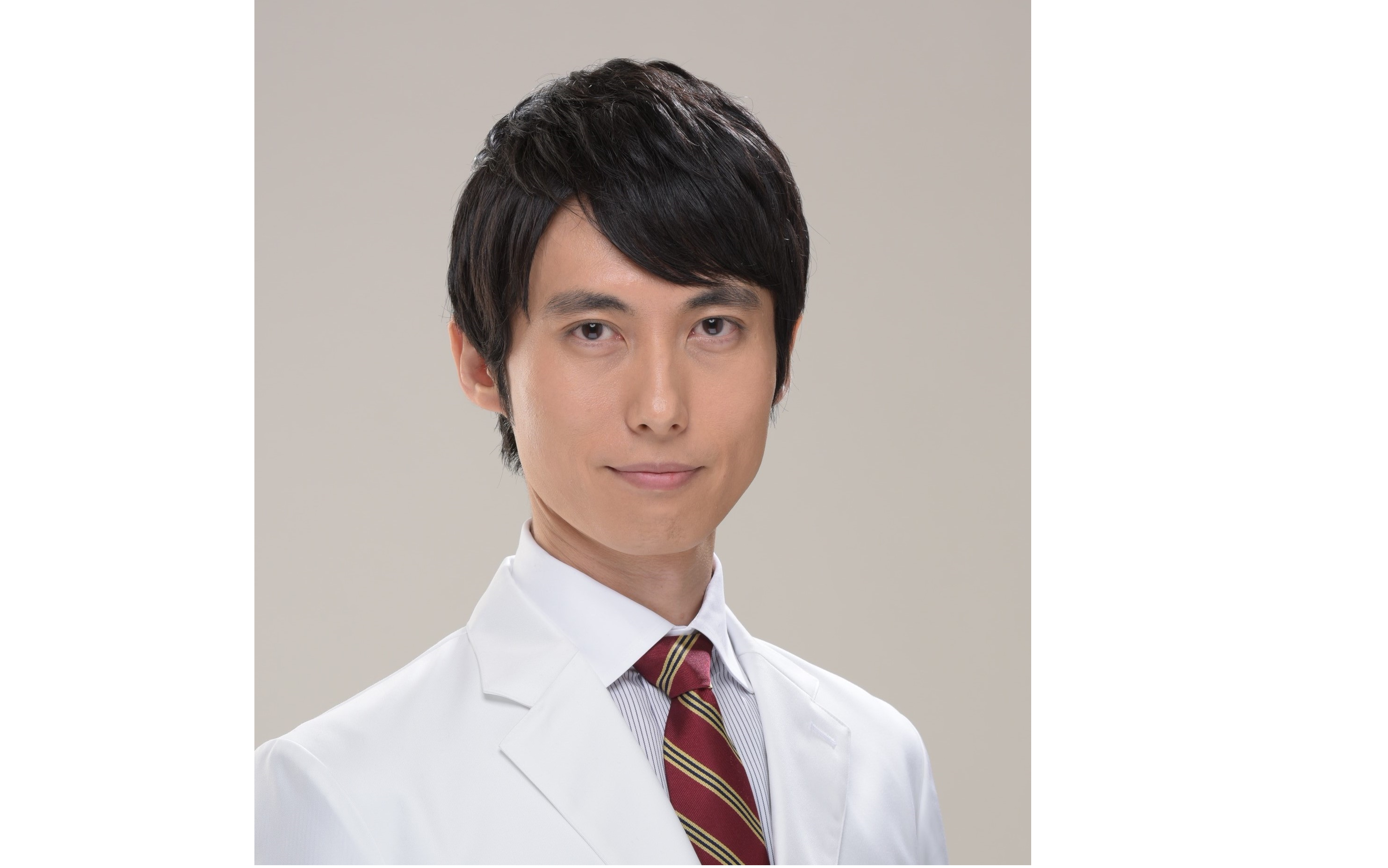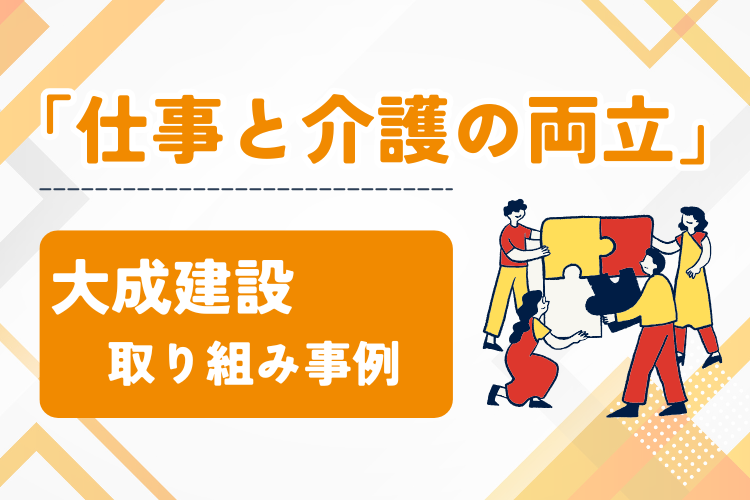「まだら認知症ってなに?」「一般的な認知症との違いは?」と疑問に思う方がいるのではないでしょうか。
まだら認知症は、脳の血管が損傷することで生じる症状のひとつです。できることとできないことに差があったり、時間帯によって症状に強弱が現れたりするため、まだら認知症と呼ばれています。一般的な認知症とは異なるため、対処するには症状を理解しておくことが重要です。
本記事では、まだら認知症に関する以下の内容を解説します。
● まだら認知症の特徴と症状
● アルツハイマー型との違い
● まだら認知症の治療・予防法
認知症に関する幅広い知識を身につけ、認知症への不安を解消したい方はぜひ最後までお読みください。
目次
・まだら認知症とは?
・まだら認知症の症状
・まだら認知症とアルツハイマー型の4つの違い
・まだら認知症の症状にばらつきがある理由
・まだら認知症の治療法
・まだら認知症の方に対応する3つのポイント
・まだら認知症の予防法5選
・まだら認知症を理解して適切な対処をしよう