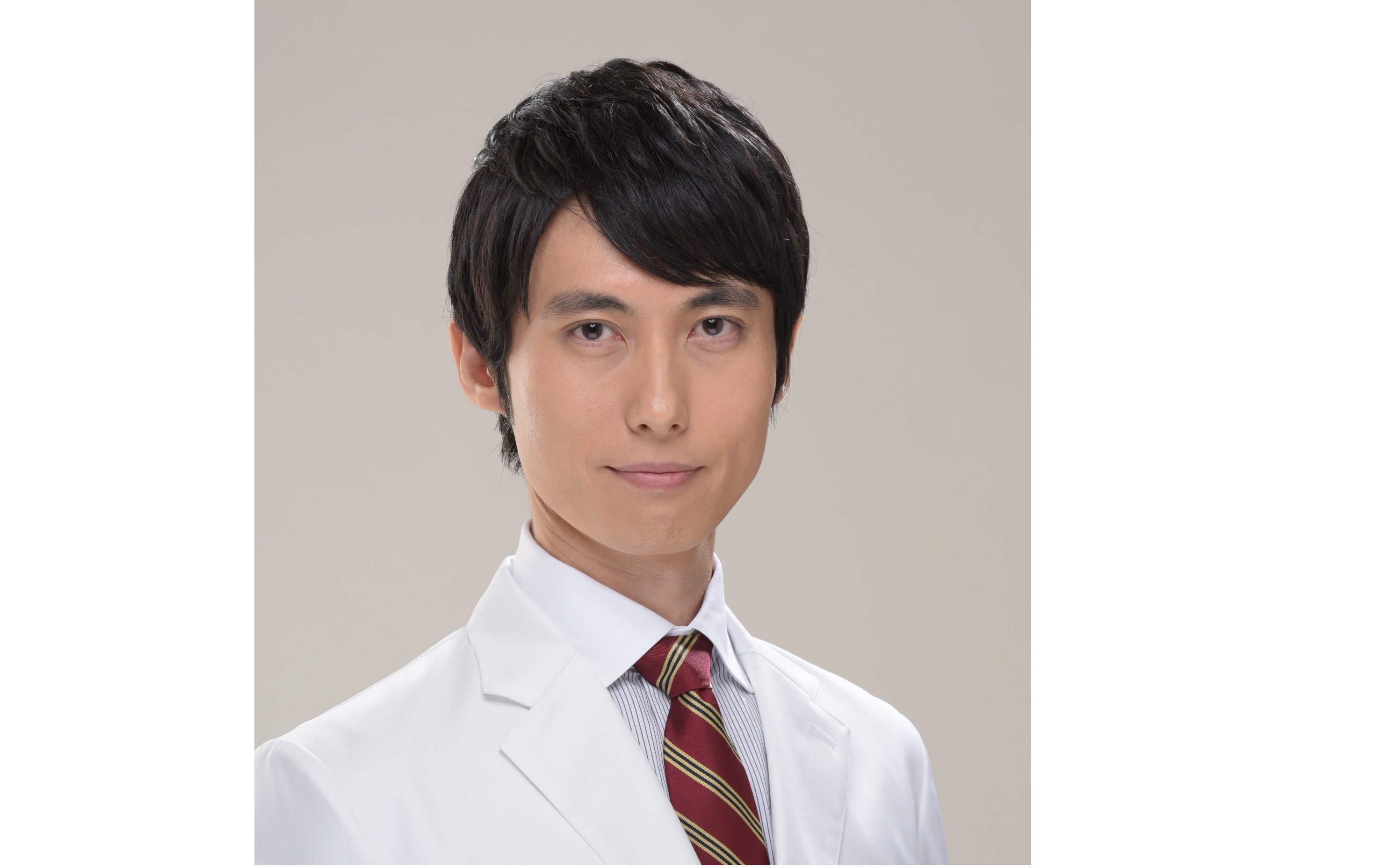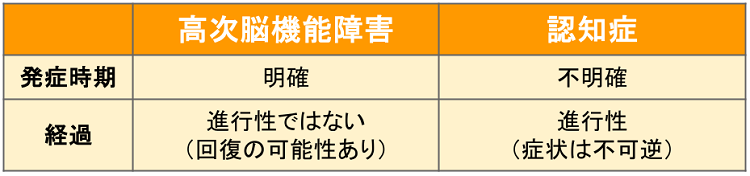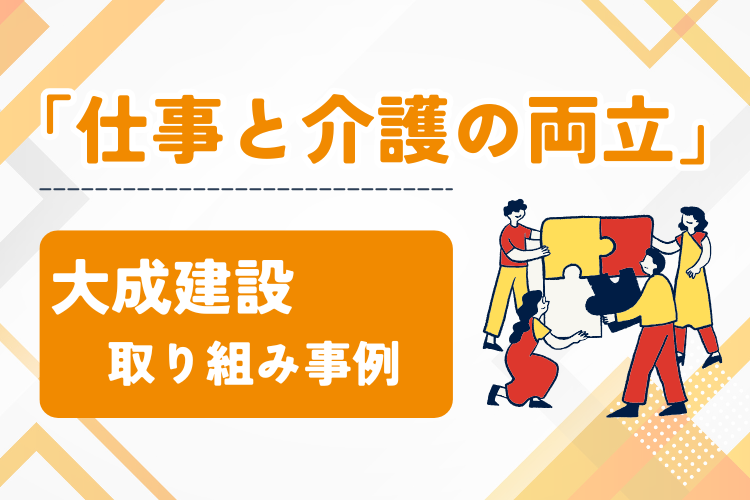「高次脳機能障害ってなに?」「どのような症状があるの?」と疑問に思っていないでしょうか。
高次脳機能障害は脳の損傷に伴う後遺症のひとつです。意図した行動ができなくなったり、注意機能・記憶に障害が生じたりするため、日常生活に支障をきたします。
生活への支障を減らすには、症状を正しく理解し、適切な治療・対処をすることが重要です。
本記事では、高次脳機能障害に関する以下の内容を、医学的根拠をもとに解説します。
● 高次脳機能障害の症状
● 高次脳機能障害の回復過程
● 症状への対処法
高次脳機能障害がある方への接し方や、関連する悩みを解決できる内容になっています。症状や今後の生活に不安を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
・高次脳機能障害とは?
・高次脳機能障害で生じる5つの症状
・高次脳機能障害と認知症の違い
・高次脳機能障害の検査・診断基準
・高次脳機能障害の経過と回復過程
・高次脳機能障害の治療法
・高次脳機能障害の症状に対処する方法3選
・高次脳機能障害の症状を理解して適切な対処をしよう