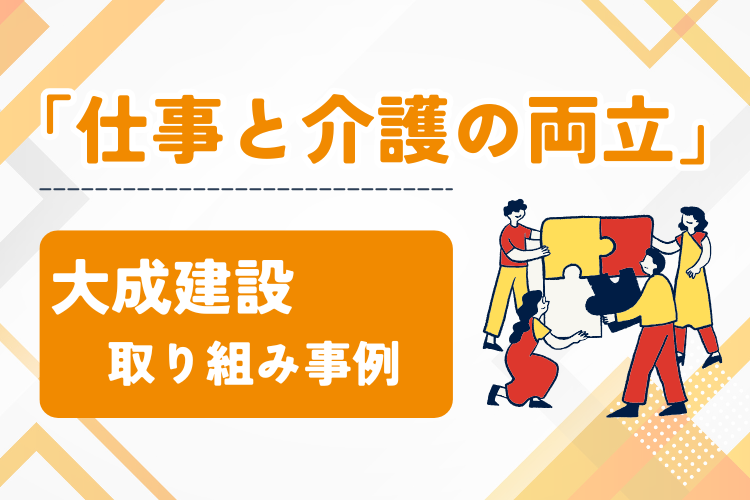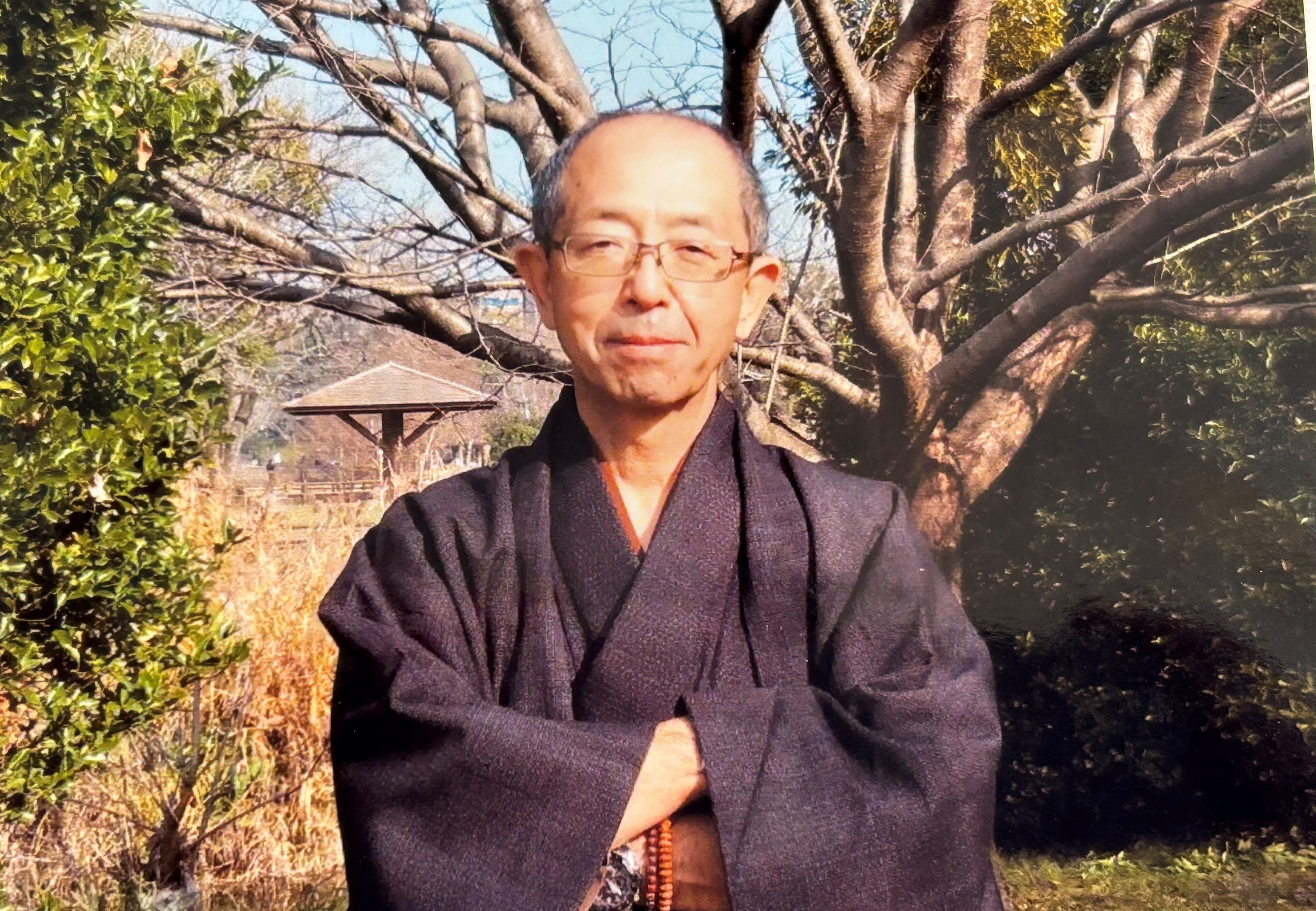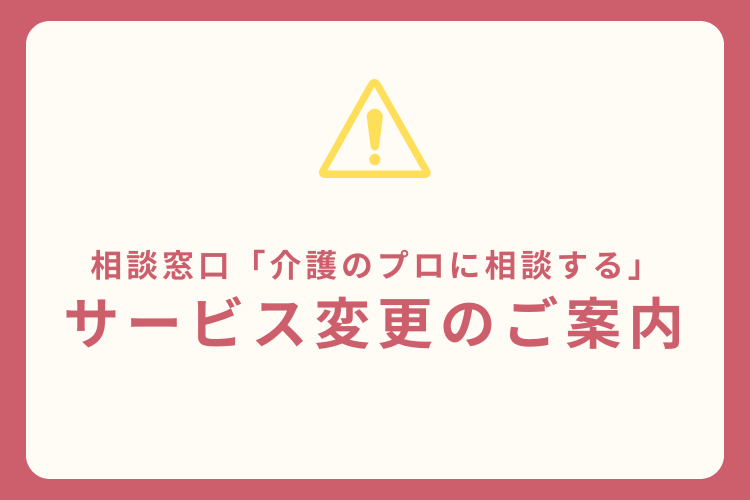脳トレは、高齢者の認知機能低下の予防をする効果があるといわれています。そのため、老人ホームや介護施設などでは、日常的に脳トレが取り入れられています。高齢のご家族やご自身のために、脳トレを取り入れたいという方は多いのではないでしょうか。本記事では、脳トレの効果や、高齢者が行うときの注意点について解説します。あわせて自宅や介護施設で行う脳トレもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
・脳トレとは
・脳トレのメリットや効果
・目的別 脳トレ13選
・高齢者が脳トレを行うときに気をつけること
・まとめ