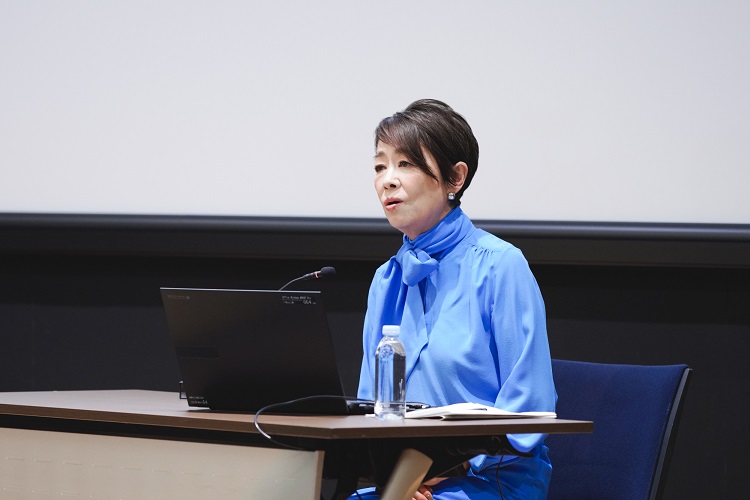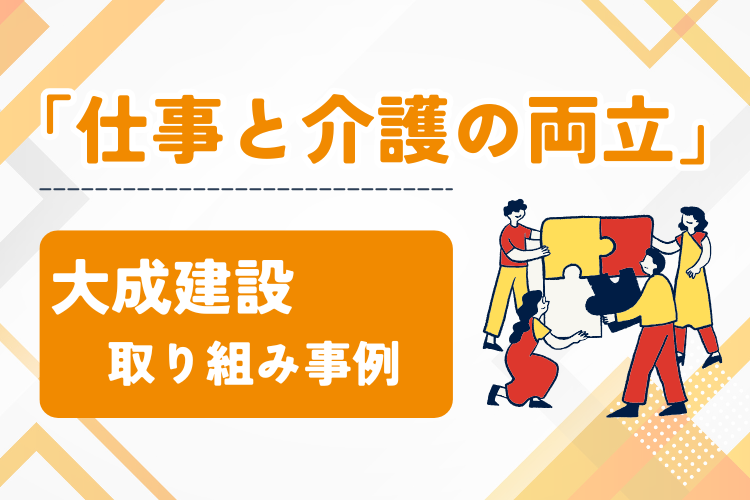時代とともに、認知症に対する理解や意識は変わってきています。特に、今年は認知症基本法が施行されたこともあり、その動きが加速しつつあります。
今回は、お母さまの介護を経験したジャーナリストの安藤優子氏と脳科学者の恩蔵絢子氏、それぞれの介護体験から浮かび上がる「新しい認知症観」について、福祉ジャーナリストの町永俊雄氏を交えてパネルディスカッションを行いました。
共生社会の実現が叫ばれる今、社会はどう向き合っていけばよいのか。そのヒントをお届けします。
安藤 優子 氏
1958年生まれ、ジャーナリスト。東京都日比谷高校から、アメリカ・ミシガン州ハートランド高校に留学。帰国後、上智大学在学中より報道番組のキャスターやリポーターとして活躍。テレビ朝日系「ニュースステーション」のフィリピン報道で、ギャラクシー賞個人奨励賞を受賞。報道の取材経験をもとにした講演、椙山女学園大学外国語学部の客員教授など、様々な場で活動している。
恩蔵 絢子 氏
脳科学者。専門は自意識と感情。一緒に暮らしてきた母親が認知症になったことをきっかけに、診断から2年半、生活の中でみられる症状を記録し脳科学者として分析した『脳科学者の母が、認知症になる』(河出書房新社)を2018年に出版。現在、東京大学大学院総合文化研究科特任研究員。共著に『なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか』(中央法規出版)、『認知症介護のリアル』(ビジネス社)がある。
町永 俊雄 氏
福祉ジャーナリスト。1971年NHK入局。「おはようジャーナル」「ETV特集」「NHKスペシャル」などのキャスターとして、経済、教育、福祉などの情報番組を担当。2004年から「NHK福祉ネットワーク」キャスター。障がい、医療、うつ、認知症、介護、社会保障などの現代の福祉をテーマとしてきた。現在はフリーの福祉ジャーナリストとして、地域福祉、共生社会のあり方をめぐり執筆の他、全国でフォーラムや講演活動をしている。
目次
・1枚の絵に浮かび上がる母の姿
・認知症のご本人が感じる“幸せ”
・尊厳に向き合う大切さ
・家族だけではなく、第三者が介入する大切さ
・「忘れたっていいじゃない」を受け入れられる社会へ