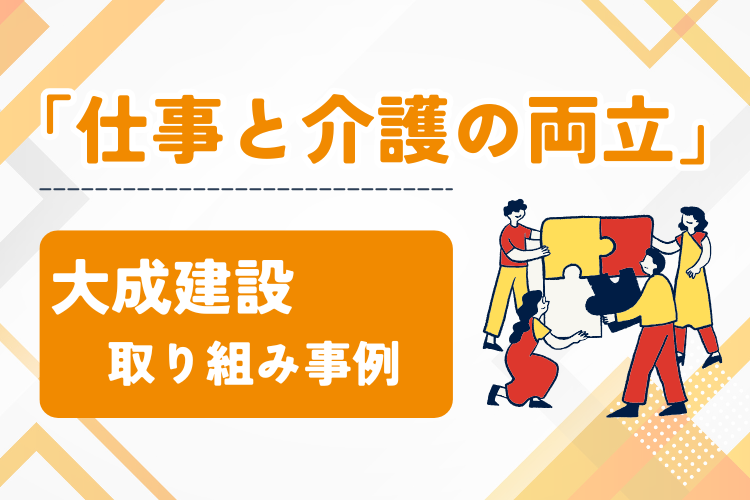近年、仕事をしながら介護をする人(ビジネスケアラー)が増加傾向にあり、2030年には約318万人に迫るといわれています。仕事と介護の両立は、ご本人やご家族だけでなく、社会全体にも影響が及びます。
そんな状況のなか、家族の介護に関わる人や周囲の人はどのような対応をすべきでしょうか。
本記事では、キャスターやジャーナリストとして活躍し、自身のお母さまの介護を経験された安藤優子さんにインタビューを実施。実際に仕事をしながら、どのようなことを考え、どのように介護に関わってきたのか。「仕事と介護の両立」をテーマに、当時のエピソードを交えながら、お話を伺いました。
目次
・仕事をしながら介護をする生活が突然はじまる
・プロが関わることで社会とのつながりが生まれる
・自分たちでどうにかする“自助”から、社会で支える“共助”へ